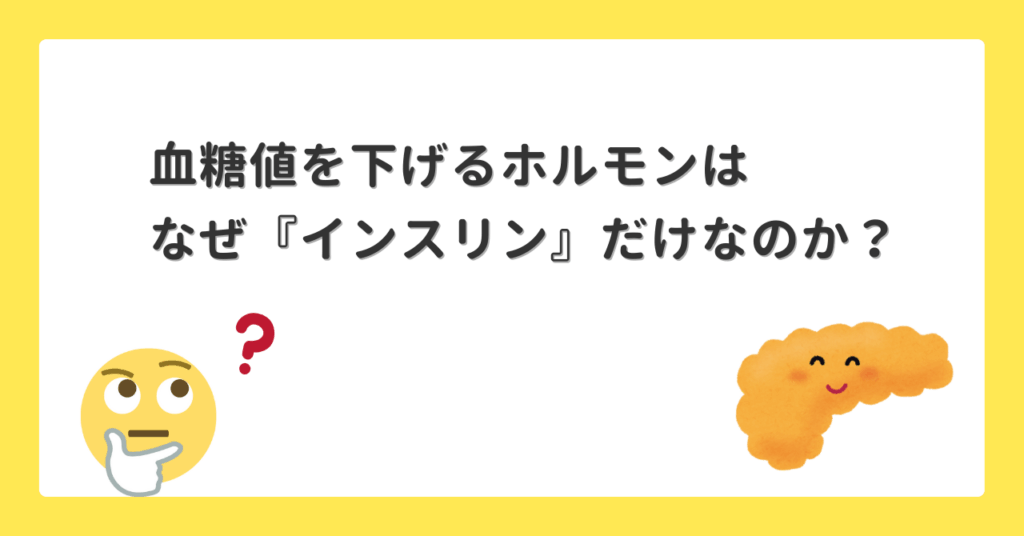グルカゴン、アドレナリン、コルチゾール、成長ホルモンなど、血糖値を上げるホルモンは、複数存在します。
しかし、血糖値を下げる役割を担うホルモンは、唯一『インスリン』だけです。
私たちの体の機能は実に良くできているのですが、なぜ『血糖値を下げる』ことができるホルモンが1種類しかないのでしょうか?
なんともアンバランスです。
もし、血糖値を下げるホルモンが複数あれば、インスリンが効かなくなっても代用できるのに。
ということで今回は、なぜ血糖値を下げるホルモンが1種類しかないのかを解説していきます。
飢餓が当たり前だった時代
人類の歴史のほとんどは、狩猟採集の時代でした。
この時代、日々の食事は保証されておらず、飢餓は常に身近な存在でした。
獲物を求めて何日も歩き続けたり、食べ物がない日も活動を続けなければなりませんでした。
私たちの体は、このような環境に適応するために進化する必要があったわけです。
血糖値を調節するホルモンの種類がアンバランスなワケ
グルカゴン、アドレナリン、コルチゾール、成長ホルモンなど、血糖値を上げるホルモンはいくつもあります。
これは狩りをしたり、逆に逃走する時、いざという時に素早く血糖値を上昇させ、活動に必要なエネルギーを確保するためです。
血糖値が低すぎる状態は生死に関わるため、複数のホルモンでそのリスクを回避しようとしました。
一方で、血糖値を下げるホルモンは唯一、インスリンのみです。
これは、生命の維持において「エネルギーを確保すること」が最優先課題だった時代の名残です。
飢餓に備えて、体は少しでも多くのエネルギーを脂肪として蓄えようとします。
しかし、血糖値が高い状態は、当時の食生活ではほとんど起こりませんでした。
そのため、血糖値を下げるための仕組みは、たった一つで事足りたのです。
環境の変化と体のミスマッチ
現代社会は、狩猟時代とは比べ物にならないほど劇的に、急速に変化しました。
特に、米などの穀物が誰もが手軽に手に入るようになったのは、人類の歴史全体から見ればごく最近のことです。
農耕が始まったのは約1万年前ですが、それでも天候不順や災害による飢饉は頻繁に起こり、食料は決して安定しているとは言えませんでした。
私たちが飢餓の心配をすることなく、いつでもお米や高カロリーな食事を手に入れられるようになったのは、日本においては第二次世界大戦後とごく最近のことです。
私たちは、エネルギーを必要とする場面が減ったにもかかわらず、高糖質な食事をいつでも摂取できる環境に置かれています。
その結果、インスリンを大量に分泌し続けなければならなくなり、インスリンを作り出す膵臓にも大きな負担がかかっています。
インスリンだけでは過剰な血糖値をコントロールしきれなくなり、肥満や糖尿病といった問題につながっているのです。
この、「飢餓に適応した体」と「飽食の現代」との間に生じたミスマッチが、
現代病の根本的な原因の一つと考えられています。
もし、狩猟時代から糖質過剰な環境だったら
もし狩猟時代から糖質過剰な環境だった場合、どうなっていただろうかと思うことがあります。
糖質を効率良く処理できるような体に進化していたのか、
インスリン以外にも血糖を下げるホルモンが作られていたのか。
はたまた現代のように糖尿病のような生活習慣病が増えて絶滅に向かっていったのか。
こんな妄想をよくしています。(笑)
まとめ
結論として、血糖値を下げるホルモンがインスリン1種類しかないのは、
人類が飢餓の時代を生き抜くために進化した、生命維持を最優先する体の名残であると言えます。
現代の糖質過剰な環境に体が適応するのは、一体いつになるんでしょうか。
僕らが生きている間にはそんな進化は起こらないと思うので、糖質を抑えた生活をした方が良いでしょう。
糖質制限を試してみたいという方は、過去の記事を参考にしてみてください。